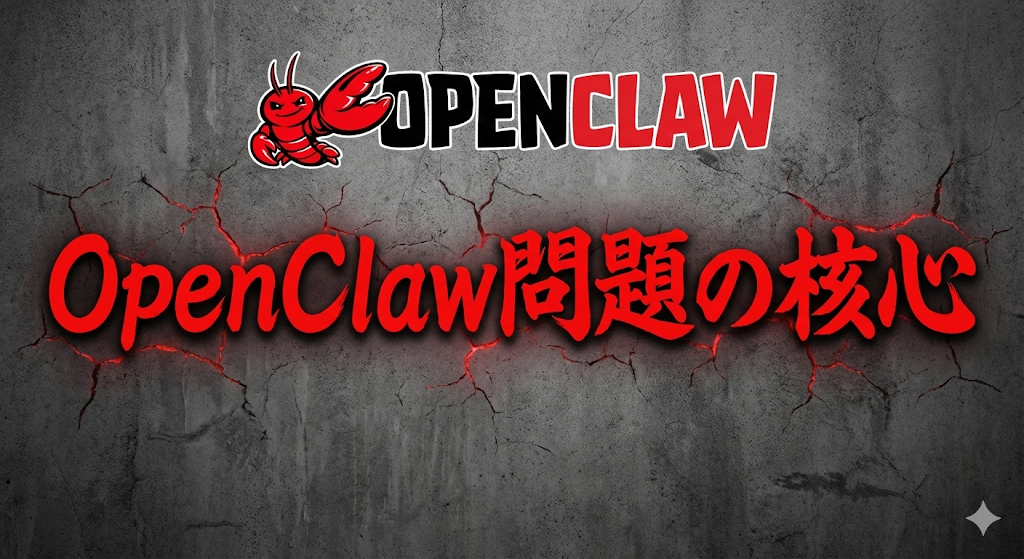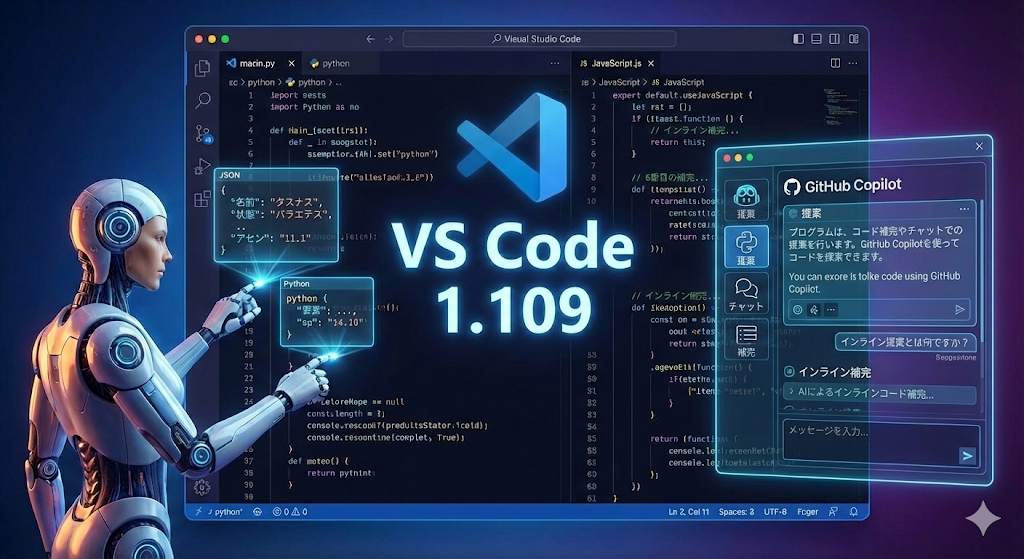生成AI活用で成果を出す企業と出せない企業の決定的な違い ー 心理的安全性とマインドセットが分ける成功と失敗

数字の裏にある「本質」
ZDNet Japanの記事によると、コロプラが生成AI活用で大きな成果を上げています。企画書作成が5分の1の時間に、業務工数を月間600時間削減という驚異的な数字です。
https://japan.zdnet.com/article/35238864
しかし、この記事で最も注目すべきは数字ではありません。
「心理的安全性を担保することが、生成AI活用推進の鍵」
コロプラ 執行役員 プロダクト開発本部 本部長の畑山氏は、この点を明確に指摘しています。新しい技術に対して、社員が「使ってもいいのか」「失敗したらどうしよう」という不安を持たずに挑戦できる環境。それこそが、劇的な成果の真の原動力だったのです。
さらに記事では、「どの生成AIツールを使うかよりも、むしろ使い方を試行錯誤するマインドが重要」という本質的な指摘もされています。
心理的安全性がなぜ生成AI活用の鍵なのか
生成AIは「正解のない試行錯誤」を要求する
従来のITツールとは異なり、生成AIには「マニュアル通りにやれば必ず同じ結果が出る」という確実性がありません。
- 同じプロンプトでも、文脈によって異なる結果が返ってくる
- 「うまくいく使い方」は、各企業が試行錯誤して見つけるしかない
- 最初の試みの多くは、期待した結果を生まない
つまり、生成AI活用は「失敗」が前提のプロセスなのです。
心理的安全性がない組織で起こること
心理的安全性が低い組織では、こんな状況が生まれます:
- 「AIを試して失敗したら評価が下がるかもしれない」
- 「うまくいかなかったことを報告すると、能力不足だと思われる」
- 「新しいツールを提案して却下されたら、時間の無駄だったと責められる」
- 「セキュリティやガイドライン違反を恐れて、誰も触ろうとしない」
結果として:
- 社員は安全な「従来通りのやり方」を選ぶ
- 生成AIツールを導入しても、誰も本気で使おうとしない
- 試行錯誤の知見が組織に蓄積されない
これが、生成AI導入が「形だけ」で終わる企業の典型的なパターンです。
コロプラの事例が示すもの
対照的に、コロプラでは:
- 経営陣が「失敗を恐れずに使ってほしい」というメッセージを明確に発信
- 利用ガイドラインを整備し、「何をしてもいいか」を明確にすることで不安を解消
- 社員が積極的に新しい使い方を試す文化が醸成される
- 試行錯誤の過程で得られた知見が組織の資産になる
畑山氏が「心理的安全性を担保すること」を重視したのは、偶然ではありません。企画書作成を5分の1の時間で完了できるようになるまでには、何度も「うまくいかない」経験があったはずです。その失敗を咎めず、学びに変える文化があったからこそ、最終的な成果につながったのです。
ゲーム会社だから成功したのか?
コロプラのような「ゲーム開発がメインの企業」は、確かに生成AIとの親和性が高い側面があります。
その理由:
- 企画書、シナリオ、UIテキストなど、テキストコンテンツ制作が日常的にある
- クリエイティブな試行錯誤を繰り返す文化が根付いている
- アウトプットの質を判断できる専門人材が社内にいる
実際、ゲーム業界やクリエイティブ産業は、生成AIの効果を実感しやすい傾向にあります。
しかし、それだけが成功要因ではありません。 むしろ、心理的安全性という「見えない土壌」があったからこそ、業務特性という「種」が花開いたのです。
もう一つの本質:「ツール」より「マインド」
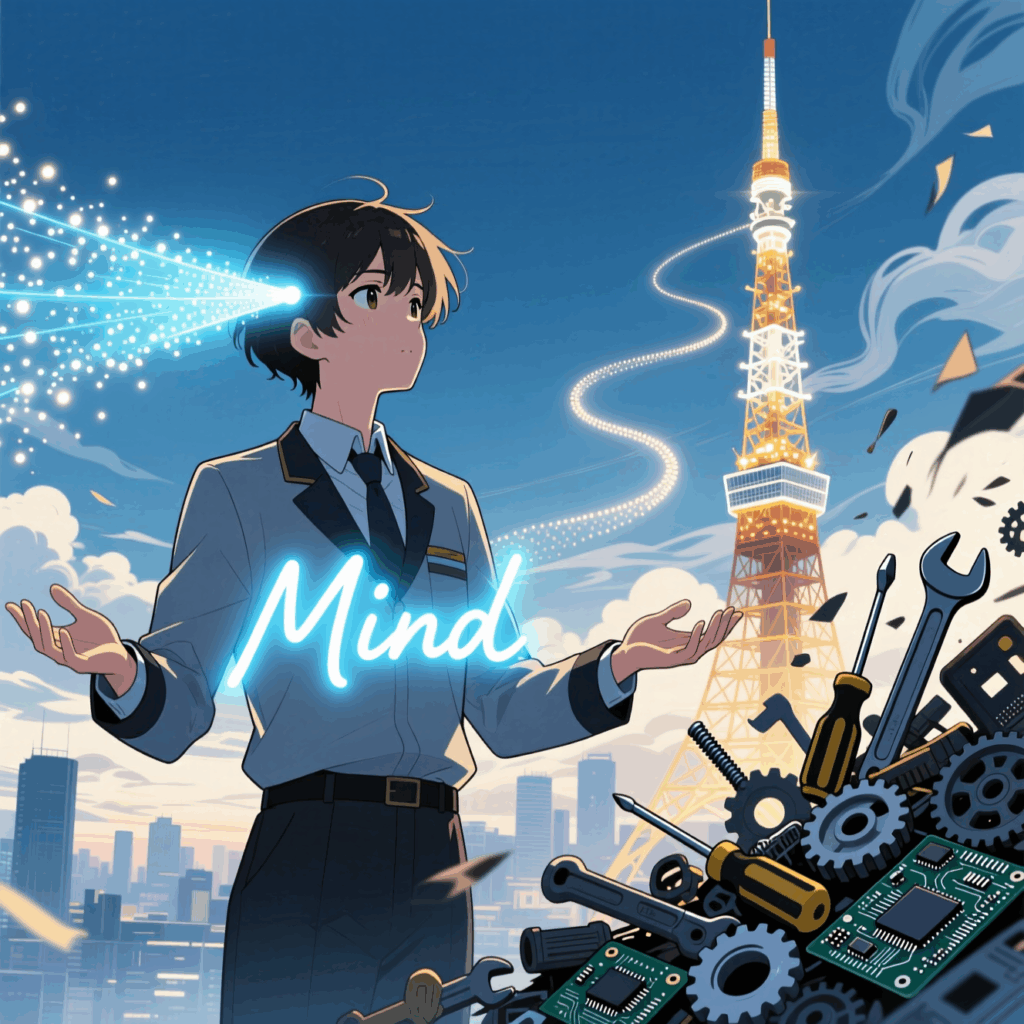
記事の中で、もう一つ重要な指摘があります。
「どの生成AIツールを使うかよりも、むしろ使い方を試行錯誤するマインドが重要」
株式会社フィールフロウでこれまで多くの企業様の生成AI導入を支援してきた経験から、この指摘は完全に正しいと実感しています。
ツール選定に時間をかけすぎる罠
多くの企業が陥る典型的なパターンがあります:
- 「どのツールが最適か」の比較検討に数ヶ月かける
- 「完璧なツール」を選べば成功すると信じている
- ツールを導入したら「あとは使うだけ」だと考える
- うまくいかないと「ツールの選択が間違っていた」と考え、別のツールを探し始める
これは、本質を見誤っています。
コロプラの事例が示すように、成果を出すために最も重要なのは:
- どのツールを選ぶかではなく
- そのツールをどう使いこなすか
- 試行錯誤を続けるマインドセット
- 失敗から学び続ける組織文化
すぐに結果を求めない姿勢
もう一つの罠は、短期的な結果至上主義です:
- 「来月までにコスト削減効果を出してほしい」
- 「すぐにROIを証明しないと上層部の理解が得られない」
- 「1ヶ月試したが効果が見えないので中止する」
このような短期的な結果至上主義は、実は心理的安全性を損ないます。「早く結果を出さなければ」というプレッシャーが、社員から試行錯誤の余裕を奪うからです。
コロプラの事例が示すのは、継続的な取り組みの重要性です。 月間600時間の業務工数削減という劇的な成果は、焦らず、失敗を恐れず、地道に積み重ねた結果として生まれています。
生成AIは「道具」ではなく「チームメンバー」

成果を出せない企業の典型的な思考パターン:
- 「AIに入力すれば完璧な答えが出るはず」
- 「人間がやることがなくなる」
- 「AIが間違えた。使えない」
この考え方は、実は「失敗を許容しない文化」と表裏一体です。AIに完璧さを求めるのは、自分自身や同僚に完璧さを求める組織文化の延長なのです。
一方、成果を出す企業の思考パターン:
- 「AIにどう伝えれば意図が伝わるか」
- 「AIの得意領域と人間の得意領域をどう組み合わせるか」
- 「AIの回答をベースに、どう磨き上げるか」
生成AIを「新しいチームメンバー」だと捉えることが重要です。 新入社員を育てるように、どう指示を出せば期待する成果が得られるかを学び、チーム全体で知見を蓄積していく。この姿勢があってこそ、心理的安全性が活きてきます。
これがまさに、コロプラが言う「試行錯誤するマインド」の本質です。
失敗を学びに変える文化
生成AIの活用には試行錯誤が不可欠です:
- 最初のプロンプトで完璧な結果が出ることは稀
- 業務フローへの組み込み方は企業ごとに異なる
- チームメンバーのスキルレベルに応じた導入ステップが必要
「失敗」を「学び」として組織的に蓄積できるかどうかが、中長期的な成果の分かれ目になります。
これは、まさにコロプラが確保した「心理的安全性」と同じ文脈です。失敗を責めない文化があるからこそ、失敗から学べる。学びが蓄積されるからこそ、企画書作成時間を5分の1にするという成果に結びつくのです。
あなたの会社でも成果を出すために
生成AI活用で成果を出すために、今日からできることがあります。
1. 心理的安全性を確保する
コロプラの事例が示すように、これが最も重要な第一歩です:
- 新しいツールを試して失敗しても、責められない雰囲気があるか?
- 「うまくいかなかった」という報告を、学びとして受け止められるか?
- 利用ガイドラインを明確にして、「何をしていいか」を示しているか?
- 経営層が「失敗を恐れずに使ってほしい」というメッセージを発信しているか?
もし答えが「No」なら、まずは小さなチームから、失敗を歓迎する文化を作ることから始めましょう。
2. ツール選定で悩みすぎない
完璧なツールを探すのではなく、まず使い始めることが重要です。ChatGPT、Claude、Geminiなど、主要なツールであれば、どれでも十分な価値を生み出せます。重要なのは「どのツールか」ではなく「どう使うか」です。
3. 小さく始めて、継続する
いきなり大きな業務改革を目指すのではなく、一つの業務から始めましょう。企画書作成、議事録要約、メール下書きなど、日常的に発生する業務が適しています。
4. チームで知見を共有する
効果的だったプロンプト、うまくいかなかった使い方、改善のアイデアを、チーム内で共有する仕組みを作りましょう。特に「うまくいかなかった事例」の共有が重要です。
5. 3ヶ月は試行錯誤の期間と位置づける
最初の1ヶ月でROIを求めるのではなく、3ヶ月間は「学習期間」として、様々な使い方を試してみましょう。この期間は「コスト」ではなく「投資」です。コロプラも、月間600時間削減という成果に至るまでには、相応の試行錯誤期間があったはずです。
6. 「試行錯誤するマインド」を育てる
これが最も重要です。完璧な結果を最初から求めるのではなく、少しずつ改善していく姿勢を組織全体で共有しましょう。
まとめ:文化とマインドセットが未来を分ける
コロプラの成功事例は、生成AIの可能性を示すと同時に、重要なメッセージを伝えています。
テクノロジーやツールそのものではなく、それを受け入れる組織文化と、どう向き合うかというマインドセットが成否を分ける。
企画書作成時間を5分の1に短縮、月間600時間の業務工数削減という数字の背景には:
- 失敗を恐れずに試せる心理的安全性
- ツール選定よりも使い方を探求するマインド
- すぐに結果を求めない長期的視点
- AIを協働者として捉える姿勢
- 失敗を学びに変える文化
これらの「見えない要素」があったのです。
ゲーム開発やクリエイティブな業務を持つ企業は確かに効果を実感しやすいかもしれません。しかし、どんな業種業態であっても、心理的安全性を育み、試行錯誤するマインドを持って取り組めば、生成AIは強力なビジネスパートナーになります。
「どのツールが最適か」を悩み続けるのではなく、「すぐに結果を」という焦りを手放し、「失敗を歓迎し、チームメンバーを育てる」ような気持ちで生成AIと向き合ってみませんか。その先に、持続可能な変革が待っています。
株式会社フィールフロウでは、生成AI活用のコンサルティングから、AI Spec Driven Developmentによるシステム開発まで、貴社の変革を総合的に支援します。技術導入だけでなく、組織文化の醸成や「試行錯誤するマインド」の育成まで含めた包括的なアプローチで、真の成果創出をお手伝いします。